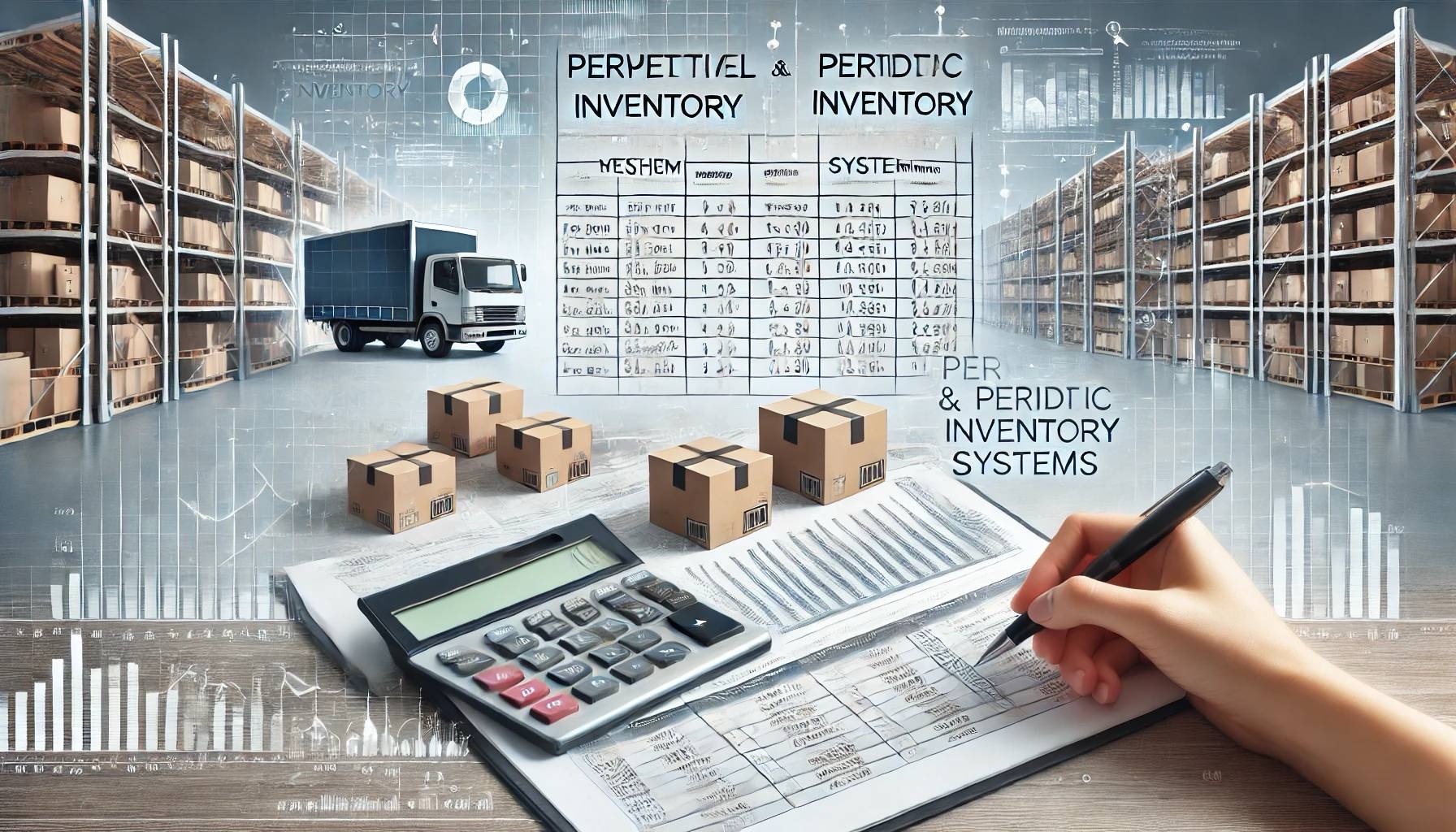企業活動として原材料や部品を購入して製品を生産し、それを販売するというサイクルが製造業では行われています。
原材料等の仕入れ単価は一定であるとは限らない(基本的には一定ではない)ため、原価管理の観点で払い出しの単価をどうするのかを決める必要があります。
払い出し単価の決め方について解説したいと思います。
購入時に費用処理するものと棚卸資産計上するものがある
原材料や部品についての会計処理には大きく分けて2種類あり、1つは購入時に費用処理する方法で、もう1つは棚卸資産資産として計上する方法があります。
まず前者の費用処理するケースですが、補助材料など金額的に重要性が乏しいものに適用されます。例えば、どの製品にも使うような汎用的なネジを少額購入したような場合、購入したタイミングで『部品費 / 買掛金』のような仕訳を登録します。
一方、後者の棚卸資産に計上するケースでは、購入時には『原材料』や『部品』のような棚卸資産資産の勘定科目で計上しておき、使用したタイミングで費用処理します。
つまり、購入時には『原材料 / 買掛金』の仕訳を登録し、使用した時に『原材料費 / 原材料』の仕訳を登録することになります。
今回の払い出し単価をどうするのかというのは、棚卸資産に計上するケースの話となります。
受払を全て記録しておく継続記録法
棚卸資産に計上するケースは、さらに2つの方法に区分することができ、その1つ目が『継続記録法』と呼ばれる方法です。
継続記録法も、この後に説明する棚卸計算法も原材料や部品を受け入れる(入庫)時に、いくつ受け入れたのか数量を記録しておく点は同じですが、使用したりして数量が減る時に記録するかどうかが異なります。
名称からも分かると思いますが、継続記録法の場合は払い出しの数量も都度記録する形になります。つまり、受払を全て記録するのが継続記録法です。この方法の場合、記録の手間はかかりますが、細かな管理が可能となります。
そのため、全ての品目に対して継続記録法を採用すると費用対効果が合わなくなることが多く、金額的に大きなものや希少なものなどビジネス上重要なものを継続記録法で管理することになります。
棚卸によって使用量を把握する棚卸計算法
一方、棚卸計算法は払い出しについては管理せず、期末等のタイミングで棚卸をすることで、使用量を認識する方法となります。
例えば、当期に100個仕入れて、期末に棚卸をして在庫が30個になっていたら、差し引きの70個を使用したとして、その分を原材料費などの費用に計上するという方法です。そのため、使用の都度記帳をする必要はないため、業務上の負荷は軽減されます。
ただ、それと引き換えに管理としては粗くなることになります。先ほどの例でいうと、70個使用したことにしていますが、実際には10個は破損して廃棄したもので、10個は盗難にあっており、実際に製品を作るのに使用したのは50個かもしれません。
継続記録法の場合は、受払と棚卸の結果で差異があれば、何が原因でそうなったのか調査のきっかけとなりますが、棚卸計算法だと記録をしていないので、異常な事態かどうかも認識出来ないということになります。
まとめ
今回は棚卸資産の受払の記帳方法について解説しました。
CO、FI、MMコンサルの場合、知っておくべき内容だと思うので、ぜひこの機会に覚えておいていただけたらと思います。